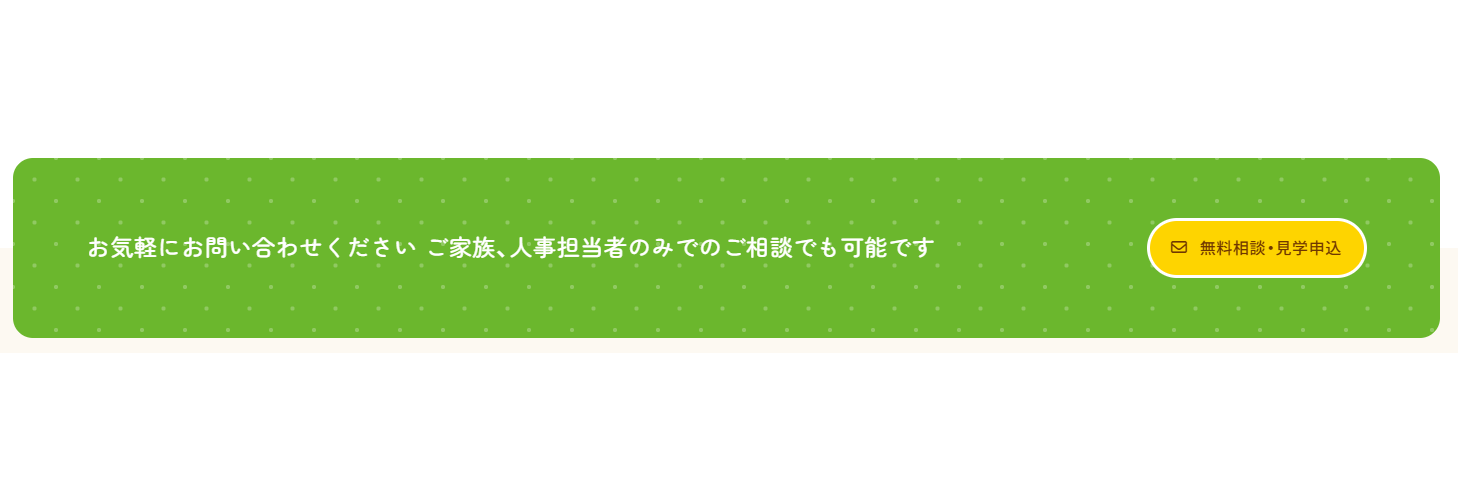こんな人は、また再休職かも?!復職に失敗しやすい人の特徴
メンタルヘルス不調から復職した後も、安定した就労を継続できない方は少なくありません。
あまり、聞きたくなかったという人もいるかもしれませんが、実際にメンタルヘルス不調で休職している人に関わっているとどうしても出会ってしまう現実なのです。
実際の現場でのご相談から見えてくるのは、再休職に至るパターンにはいくつかの共通点があるということです。
今回は、リワーク施設や企業支援の現場から見えてきた再休職に繋がりやすい主な要因4つをご紹介します。
この4つの要因とは、以下の通りです。
- 診断書の拡大解釈
- 焦燥感
- 罪悪感
- 元気を装っている
お忙しい方は、気になる要因だけでも見て頂けると参考になるかと思います。
また、再休職しにくい効果的な対策もご紹介しますので、ぜひ試してみてくださいね。
要因1-診断書の拡大解釈

休職(企業によっては、病気休暇扱いや有休休暇後に休職など)に入るためには、多くが主治医からの診断書かと思います。
大体の場合は、そこに「3ヶ月の療養が必要」などの休職期間(休養)が記載されていることが一般的です。
ここで、起こりえることが「3ヶ月休めば良いのか」と考えてしまいやすいことです。
これは、3ヶ月休職すれば「働いても良いですよ」という意味ではないということです。
これを深く考えずに都合の良いように解釈をしてしまって、休養期間に復職の準備をせずに復職に臨んだ結果、産業医から「復職不可」や「リワークに行ってください」と言われてしまう人が多くいます。(中には、これで産業医と揉めてしまうことになる人も数人おられるようです・・)
主治医の先生は、現在とこれまでの経緯から「3ヶ月の休職が必要」だという判断をしているだけに過ぎないのです。
これは、「3ヶ月後に復職をしても良い」という判断をしている訳ではありません。
メンタルヘルス不調というのは、それぐらい判断しにくいことであり、「嫌やな」と感じてしまう人が多いかもしれませんが、主治医に自身の困っていることや状態、服薬状況等は伝えることが重要です。
主治医も判断するのに、情報が必要になります。その情報が多ければ多いほど、精度が高ければ高いほど、判断が的確になっていきます。
つまり、自分の状態を判断してもらうには「自分の状態を伝える」ことが、必要になってきます。
要因1-診断書の拡大解釈の対策
- 主治医への相談
- 復職についての情報収集(主治医、職場)
- 自分の状態把握
上記でも記載した通り、やや面倒くさいかもしれませんが復職するのに望ましい状態などを主治医に聞いて相談しておくことが必要です。
また、職場側とも相談することは必要です。
職場側は、従業員を守るために安全配慮義務を負っています。
つまり、復職しても悪化しないか、仕事ができる状態(=職位や職務に定まっている業務を一定の評価で達成できるのか、)休職した原因に対して対策できているのか等を判断しています。
そのため、会社は判断基準を満たせているかや復職するまでの過程をきちんとクリアしているかといった復職までの計画が定められていることがほとんどです。
休職して復職する方は、自分の思いや考えだけで復職を受け入れてもらえるわけではなく、上記の会社の復職までの計画をクリアできるように復職準備が必要です。
計画をクリアできているとなれば、会社側は復職許可を出ししやすくなるようです。
一方で、復職できるかの判断材料が少ないと産業医面談等で復職許可が下りないといった事例も良くお聞きします。
その中で多いのは、「休職期間中、自宅でいることがほとんどであった」、「1時間ほど散歩や買い物に行っていた等の少ない日中活動」などが散見されます。
そのため、事前にご自身でも職場に復職するための要件を聞いておけると準備がしやすいでしょう。
要因2-焦燥感

「会社に迷惑をかけている」、「収入面で不安がある」、「早く働かなければ」という焦りから、十分に回復する前に復職してしまうケースがあります。
休職をすると、休んでしまったことによる「自信の喪失」や「周囲からの目線」が気になってしまう場合があります。
そんな時に、その状態から一刻も早く抜け出さそうとして、「焦燥感」が強くなっていくことがあります。
これらは、うつ病の症状の一つでもあり、真面目な人であれば尚更、感じやすいといえます。
その結果、復職を急いでしたものの、職場から再休職を告げられてしまうことがあります。
これまで、復職後の継続率が研究でも明らかにされており、何かしらの支援を受けて復職している人は、再休職せずに継続している割合が高くなるという研究データがあります。
つまり、焦って復職を急いで再休職を繰り返して自信をなくすよりもしっかりと現状の自分自身の状態を見つめて、再休職しないよう取り組むこと(=リワーク)が復職への近道となります。
要因1-焦燥感の対策
重要なことは、自分ひとりで急いで決めようとせずに主治医や専門家に相談しましょう。
焦る気持ちだけで行動するのではなく、復職した後の生活や健康状態についても検討してみることが重要です。
方法としては、主治医などに「同じように焦燥感を抱いている人はどうしていったのか?」など他の人の対策や事例も参考になるので、質問してみることも必要です。
また、焦燥感に苛まれている状態では考えにくいため、気持ちを落ち着かせるために瞑想やマインドフルネスなど取り入れてみても良いでしょう。
多くの問題は今すぐには、解決することは少ないです。まずは、自分の状態を冷静にするためにも焦燥感を軽減する取り組みが効果的です。
気持ちや状況の整理から始めてみること、対策や取り組み方を計画すること等、今できることを一緒に考えてもらうことが重要です。
要因3-罪悪感

メンタルヘルス不調で休職している方の多くが経験するのが、「職場に迷惑をかけている」「自分だけが弱い」といった強い罪悪感です。この罪悪感は、休職期間中の回復を妨げる大きな要因となっています。
罪悪感が生まれる背景には、「働くことが当たり前」「休むことは甘え」といった社会的な価値観があります。
特に責任感が強く、完璧主義的な傾向がある方ほど、この罪悪感を強く感じる傾向があります。
「同僚に負担をかけている」「会社に損失を与えている」と考え続けることで、本来必要な休養期間でも心が休まることがありません。
さらに問題となるのは、この罪悪感が「自分は価値のない人間だ」「復職しても役に立たない」といった自己否定的な思考パターンを強化してしまうことです。
罪悪感→自己否定→抑うつ気分の悪化→さらなる罪悪感、という悪循環に陥り、回復が遅れてしまうケースが多く見られます。
また、罪悪感は「早く復職しなければ」という焦りを生み、十分な回復を待たずに復職を急ぐ原因にもなります。結果的に再度体調を崩し、より長期間の休職が必要になってしまうという皮肉な状況を招くことがあります。
要因3-罪悪感の対策
まず重要なのは、罪悪感の根底にある思考パターンを客観視することです。
「休職は治療の一環である」「適切な休養は会社にとってもプラス」といった現実的な視点を持つことが必要です。
主治医やカウンセラーと一緒に、自分の思考の癖を振り返り、より建設的な考え方を身につけていきましょう。
職場の人事担当者や上司との定期的な連絡も有効です。
多くの場合、職場側は「しっかり休んで回復してほしい」と考えています。
実際の職場の状況や同僚の反応を正しく把握することで、過度な罪悪感を軽減できることがあります。
「完璧でなくても良い」「人間には休息が必要」といった考えを少しずつ受け入れることが大切です。
日記や感情記録をつけて、自分の感情の変化を客観視する練習も効果的です。
また、同じような経験を持つ方との情報交換や、家族・友人からのサポートを積極的に受け入れることも重要です。
要因4-元気を装っている

周囲に心配をかけまいと「元気を装う」行動です。
この行動は、本人の回復状況を正しく把握することを困難にし、適切な治療やサポートの機会を逸してしまう要因となっています。
元気を装う背景には、「弱さを見せたくない」「周囲に負担をかけたくない」という心理があります。
特に家族の前では「心配をかけたくない」という思いから、実際よりも調子が良いふりをしてしまうことがあります。
また、主治医の診察時においても、「良くなっていると思われたい」「期待に応えたい」という気持ちから、症状を軽く話してしまうケースが見られます。
ただ、実際には「実は眠れていない」ことや「考えが巡ってしまうこと」などで困っている場合も見受けられることがあります。
この「元気な演技」は、本人にとって非常にエネルギーを消耗する行為です。
本来は休養が必要な状態にも関わらず、周囲に合わせて活動的に振る舞うことで、回復が遅れてしまいます。
さらに、周囲が本人の真の状態を把握できないため、必要なサポートが提供されない、または不適切なタイミングで復職を促されてしまうリスクがあります。
産業医面談においても、元気を装うことで実際の状態とは異なる印象を与えてしまい、復職可否の判断に影響を与える可能性があります。
結果的に、準備不足での復職により再び体調を崩すという悪循環に陥ることがあります。
要因4-元気を装っているの対策
最も重要なのは、主治医や産業医、職場の担当者に対して正直に自分の状態を伝えることです。
「良く見られたい」という気持ちは理解できますが、正確な情報がなければ適切な治療計画や復職プランを立てることができません。
症状の波、調子の良い日と悪い日の違い、具体的な困りごとなどを率直に共有することが、真の回復への第一歩となります。
家族や親しい人への開示については、段階的に行うことをお勧めします。
まず、「完全に元気ではないこと」「サポートが必要な部分があること」を伝え、具体的にどのような支援を求めているかを明確にしましょう。
多くの場合、周囲の人は「どう支えれば良いかわからない」と感じています。
具体的な要望を伝えることで、適切なサポートを受けやすくなります。
日々の体調や気分の変化を記録する習慣をつけることも効果的です。
客観的なデータがあることで、診察時により正確な情報を提供できます。
また、自分自身も体調の波やパターンを把握できるため、無理をしがちなタイミングを事前に察知することができるようになります。
睡眠時間、活動量、気分の数値化などを通じて、「元気を装う」のではなく「現実的な状態把握」を心がけることが重要です。
まとめ

全てに共通するのは、客観的な判断に基づいておらず、自身の感情や自分に都合の良い情報だけで判断して行動している点です。
「復職する」ことが目的になってしまっているなと感じている人が多いです。
もちろん、どうしても復職しないといけない事情がある方もおられると思います。
それも選択肢の一つであることは承知しています。
ただ、長い人生で考えていただくと「今、この状態で復職すること」が果たして良いのか?と「将来の健康」についても考えてほしいと考えています。
復職を希望している人にお伝えしているのは、葛藤が生じたとき(例えば、「朝起きれないけど1ヶ月後に復職しなければ」「職場の人に申し訳ない」など)、優先してほしいのは「ご自身の健康」です。
なぜなら、これまでご自身の健康を後回しにしてきた結果が現状だからです。
同じように、ご自身の健康管理ができない状態で戻ると同じ休職に至る確率は高くなります。
その様な選択肢を取らざる得ない状況を避けるためにも、1人だけで背負いすぎずに周囲のサポートを頼ってみることオススメします。
まずは、あなたの頑張っている部分、気になっていることを誰かに知ってもらうことが何よりの再休職予防につながると思っています。
もし、1人で行えるのか自信がない方、長期的に相談する場所や相手が探している方は、お気軽にご相談ください。